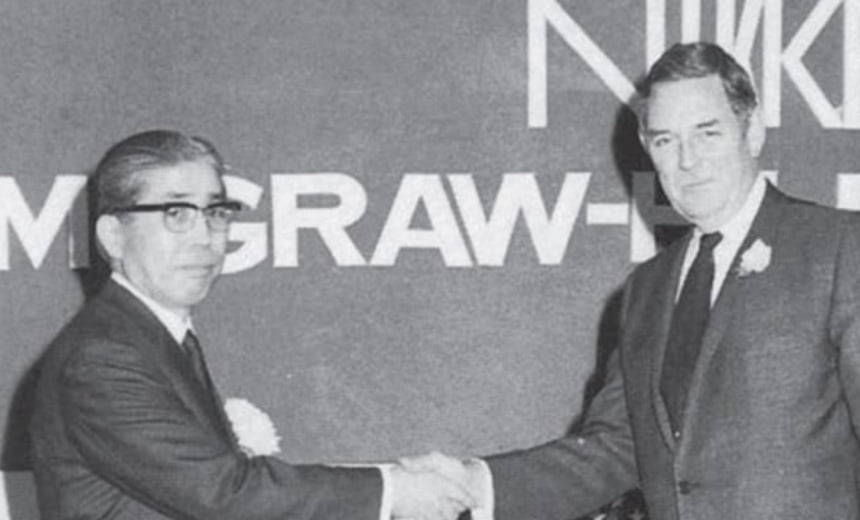[日本経済新聞社140年史特別コラム 論説主幹(当時) 芹川洋一]
日本経済新聞には「貫く棒の如きもの」があると思う。それは自由主義(リベラリズム)と現実主義(リアリズム)という物の考え方ではないだろうか。 少なくともこの二つを心棒にして、われわれは物事をとらえている。それがどのようにして、つちかわれてきたのかと思いめぐらすとき、ある人物につきあたる。中外商業新報の編集局長をつとめ、日経の社長だった小汀利得だ。小汀を抜きにしてジャーナリズムとしての日経は語れない(文中敬称略)。
1. 遅れてきた新聞記者
小汀は1889年(明治22年)、島根県出雲市で生まれた。上京して新聞配達をしながら学校に通い、早大に入学、1915年(大正4年)首席で卒業した。安部磯雄(早大教授・衆院議員・社会運動家)の推薦で、島田三郎衆院議長(言論人・立憲改進党結党に参加・普通選挙実現に尽力)の秘書官になり、2年間つとめた。
島田議長の退任とともに横浜にあった増田貿易という会社に入社したものの会社整理で退社、21年、中外商業新報に入社した。32歳。遅れてきた青年だった。
6年後の27年(昭和2年)に経済部長、34年には編集局長とそのあとはとんとん拍子だった。

本名は「おばま・としえ」だが、小汀もそうだし、利得もなかなか正しく呼んでもらえなかった。本人が「『おまえは経済問題を取り扱うところから、利得なんて皮肉なペンネームをつけたのだろう』としばしばいわれるが、これは本名でトシエと読む」とわざわざ最初のころの著書(『街頭経済学』千倉書房・31年刊)で注釈をつけているほどだ。
ただ、いっぱんに「りとく」さんといわれた。後年、レギュラー出演しその名を全国に広めたTBS系列の『時事放談』で、相方の細川隆元(元朝日新聞編集局長)がそう呼びならわしたためだ。
ある年齢から上の人の記憶に残るのは毒舌で、66年のザ・ビートルズの来日公演で日本武道館をコンサート会場として使うのを批判するなど、ちょっぴり物わかりの悪い頑固じいさんのイメージだろう。
もちろんそうした面がなかったわけではないだろうが、中外商業の記者時代から、47年の占領国軍総司令部(GHQ)による公職追放で社長をしりぞき、50年の追放解除のあと日経顧問で言論活動をつづける中でも、一貫していたものがある。
それは自由主義者としての顔である。
もうひとつ、現実主義者としての顔もあわせもっていた。
さらに付けくわえるならば、啓蒙主義者といっていい顔だ。一般向けの著書も数多く、書いたものもできるだけ平易に、かみくだこうとしている。目線の低い市井のエコノミストの顔と言いかえてもいい。時事放談の毒舌にしても、物事の本質をずばりとつかみ、わかりやすく伝えたいという思いからだったのだろう。
自由主義者・現実主義者・啓蒙主義者――3つの顔を持つ小汀。「中正公平 わが国民生活の基礎たる経済の平和的民主的発展を期す」という日経の社是。経済が平和的民主的に発展するには自由でなければならない。経済はリアルなものである。小汀の自由主義と現実主義は、おのずと日経の社是と重なってくる。啓蒙主義はもともとメディアが果たす役割だ。
先達のジャーナリストを通して、見えてくる日経の姿がそこにある。
2. 自由主義者
「ヘナチョコ」「ヘッポコ」ーー小汀が軍人、官僚に冠する決まり文句だった。
日経朝刊の71年2月に掲載した『私の履歴書』で「あのころ(編集局長当時)一番不愉快だったのは政府の言論統制である」と振り返っている。皇室に関する記事で発禁になったり、毎日のように「記事差し止め」の通達があったりなどと「バカげた時代であった」といきどおる。
「ぼくはそういう時代でも『大機小機』や社説で攻撃すべきことは勇敢に攻撃した。その時々の政府や軍部の施策で気にくわないことがあると『ヘッポコ軍人』とか『ヘナチョコ官僚』とさんざんコキおろしたものだ」
もっとも軍部に批判的な記事が出ると、しばしば軍から小汀編集局長に呼び出しがかかった。
『毒舌闘争50年』(日新報道・70年刊)によると、次のような場面がくりひろげられた。
九段下にあった憲兵隊へ「小汀ですが」と出頭すると、軍曹が出てきて「どうぞこちらへ」といって半地下室へ連れていき「しばらくお待ちください。誰々が来ますから」といって、威嚇するような、ガチャンと音をさせて戸を閉めていく。
2時間ぐらいたつと少佐がやってくる。
「小汀さん、今朝のは困ります。ああいう記事は」
「ハァ、何でしたかね」
「これこれの記事ですよ」
「あ、あれですか。あれは真実であるし、別に国の害にはならないと思って、書かしたんだが、いけないですかね」
「そりゃ困ります。ああいうことを書かれると、東条閣下がおこりますからね」
「それじゃ、ボクが直接、閣下に謝ってきますよ」
「そんなこと、おっしゃっても困ります。まあ今後どうか気をつけて下さい」
腹の中では「クソッ!この憲兵野郎のヘボ!」と思いながら、社へ帰ったことなど度々あった、と回顧している。
小汀が一本芯の通った自由主義者だったのはまちがいない。
作家の三好徹著『評伝 緒方竹虎』(岩波現代文庫)に象徴的なエピソードが出てくる。
38年4月に成立した国家総動員法をめぐって、各新聞の代表が帝国ホテルに集まって対応を協議した。
草案には、国防目的の達成のため「必要あるとき」は新聞記事の制限や禁止のほか、発行停止の規定まで入っていた。
朝日新聞の主筆だった緒方竹虎(副社長から後に自由党総裁)は、新聞に関するくだりを削除するよう関係方面に働きかけるべきだ、といった。
そのとき「そんなことではいけない。新聞界が自分たちに関係のある部分だけ削ってくれといったのでは、必ずやり損なう。この法案全体がいかんという態度をとらなくてはいけない」と主張したのが小汀だった。
三好徹は「小汀の意見は正論であった。が、結局は彼に同調するものはなく、新聞条項も発行停止が削られたにすぎなかった」と書いている。
日経OBの話も紹介したい。社内報・太陽樹94年8月号で「先輩が語る日経ー戦後50年特別企画」と題したインタビューを掲載。そのなかで荻原伯水(35年=昭和10年=入社・外報部長、編集局長などを歴任)が小汀の思い出をつぶさに語っている。
37年、日中戦争がはじまり、荻原は上海特派員を命じられる。編集局長の小汀のもとに挨拶に行った。
「いいか荻原君、君を上海に送るのは、兵隊のまねをして最前線に飛び出したり、鉄砲玉にあたったりするためじゃあないんだ」
「上海は国際都市で、金融、その他の重要な政策がぶつかりあっている。上海にはリースロス(蔣介石の政策顧問で中国の通貨制度の改革を行う)というイギリス人のもとで働いているエドワード・カーンという人間がいる。大変有能な人物なので、この人に会って取材しろ。上海をどう復興させるかということは日本経済にとっても大問題だ」
小汀に言われた通り、荻原はエドワード・カーンを取材する。カーンは「戦争は勝っても負けても両方にとって損だ。グレートロスである。だから1日も早くやめなければならない。それが私の意見だ」と述べた。
荻原は困ってしまう。「戦争は早くやめるべきだ」などといったら憲兵隊に捕まってしまう。しかし取材したからには書かねばならない。原稿をまとめ、あとは本社の判断と意を決して送稿した。
送られてきた紙面をみると「戦争は両方の損失」と4段の記事になっていた(37年12月28日付中外商業朝刊)。
荻原は「戦争がはじまったばかりの燃えさかっているときに、『戦争ではなくその先を考えろ』という指示をいただいたことは非常に感激でした」と回顧している。
小汀は決してお先棒をかついで戦争に協力したのではない。軍部と対立し、日独伊枢軸にも反対した。
だが37年から42年まで中外商業の編集局長で、43年以降は大日本言論報国会の参与として戦争に協力したという理由で47年10月、公職追放された。45年7月からつとめていた社長職(当初は日本産業経済新聞=中外商業が戦時統合で改組=・46年に日経に改称)を離れた。
3. 現実主義者
なんと言っても小汀が広く知られるようになったのは金解禁反対の論陣を張ったことだ。ここに現実主義者としての顔がのぞく。
小汀の証言があるので、それをもとにしながら、ふりかえってみよう。放送 タレント・三国一朗の司会による東京12チャンネル(現テレビ東京)番組「私の昭和史」に69年3月、出演した際のものだ(同報道部編『証言・私の昭和史』所収)。
金解禁は浜口雄幸内閣が30年1月に断行した昭和初期の日本の経済社会をゆるがす一大事件だった。第1次世界大戦中の17年9月、当時の寺内正毅内閣のもとでおこなわれた金輸出禁止を解除するもので、13年ぶりの金本位制への復帰となる。
百円札や十円札と金貨との引き換えを再びできるようにし、金の輸出入を自由にして、通貨の価値を大戦後のインフレ以前の状態に戻すのがねらいだった。以前の1ドル=2円の為替レートによる旧平価による解禁だ。その後の実勢レートにそった新平価(1ドル=2円50銭程度の円安水準)ではなかった。
第1次大戦がはじまると各国はこぞって金輸出を禁止、日本もこれにならった。戦争がおわると各国とも金解禁をおこない金本位制にもどした。日本も同 じように金解禁をめざした。ところが23年の関東大震災、そのあとの金融恐慌もあり、なかなかタイミングをつかめないでいた。
29年7月2日に発足した民政党の浜口内閣は、施政方針の柱に金解禁の断行をかかげた。「危機に立つ日本経済を常道にもどすため」におこなうもので 、必ず景気は良くなると説いた。
金解禁をめぐり、当時の金融界、言論界などの大勢は井上準之助蔵相の断行論を支持していた。これに真っ向から反対したのが中外商業・経済部長の小汀のほか、東洋経済新報・主幹の石橋湛山、経済評論家の高橋亀吉、時事新報(のちに読売新聞)・経済記者の山崎靖純の4人だった。「4人の侍」といわれた。
彼らは、1ドル=2円の旧平価による金解禁を実施すれば不景気が到来、もしどうしてもというのなら実勢の為替レートにそった円安水準の新平価で解禁すべきである、と主張した。

当時の中外商業の紙面をみると、金解禁への強い疑念を示している。
内閣発足から4カ月半たった11月21日、政府は翌30年1月11日からの金解禁実施の大蔵省令を公布した。編集紙面ではすぐさま翌々日11月23日付から「金解禁実施と財界の将来」と題する10回連載の記事を掲載した。
そこでは、金が海外に流出し、物価が低落、農村や商工業に大きな打撃を与えるのは必至なのに政府は何の対策もとっていないと厳しく批判。「前途に幾多の困難の伴ふことはけだし免れがたきところであらう」という言葉で連載を締めくくっている。
予言は的中した。悪いことに29年10月、ニューヨークのウォール街の株価暴落に端を発する世界恐慌がおこった。30年1月からの金解禁を前にして、たちまち日本に波及してきた。
物価は暴落、倒産が急増し、失業者が、ちまたにあふれた。特に農村では農産物価格が暴落し、凶作もあって悲惨な状況になった。金解禁は裏目に出た。大不景気を招いてしまったのだった。
31年12月に政友会の犬養毅内閣が成立し、ただちに金輸出を再禁止した。だが金解禁の失敗は単なる経済政策にとどまらなかった。農村の疲弊から政党不信、5・15事件、2・26事件へと国家が突き進んでいくひとつのきっかけをつくったというのが小汀の指摘である。たしかにその通りだった。
ではなぜ金解禁に動いたのか。『証言・私の昭和史』での小汀の解説は明快だ。
経済学者も経済界も、経済が実際にどう動いていくかを判断できるリアリスティックな目を持っていなかったというわけだ。
小汀の証言をさらに聞こう。
金解禁をリードした井上蔵相の評価はとりわけ手厳しい。
金解禁問題は現実を直視し、経済の生の動きがわかっていた小汀の面目躍如たるものがある。
4. 啓蒙主義者
3つ目の啓蒙主義者の顔には、常に毒舌という形容詞がついてまわった。
小汀の名前が世間に広く知れわたったのは日曜の朝に放映していた『時事放談』に出演するようになってからだが、57年から70年まで13年間に及んだ。
細川隆元とのかけ合いの妙で人気を博したものの「番組発足当時は細川隆元君とうまく歯車が合わず、落語家の林家三平から、話の呼吸について親切な忠言もあった」(『私の履歴書』)というから、けっこう苦労もしたらしい。
「ぼくも細川君も歯に衣着せずいいたい放題しゃべりまくり、人気番組になった」というように、毒舌が小汀のトレードマークになった。番組を降板したあとに出版した一代記の題名も『毒舌闘争50年』だった。
もっとも毒舌はテレビ用に定着したイメージではなく、もともとそういう性格だったようだ。
小説家の山田風太郎著『戦中派虫けら日記』(ちくま文庫)に小汀の名前が出てくるくだりがある。昭和19年6月12日だ。「午後、二時間にわたり『大戦下の政治経済』なる題目で、産業新聞主筆小汀利得氏の講演あり」とある。
おおざっぱで、ずけずけと本音で語るタイプだったのは間違いない。だから聴衆に受けた。
それは小汀とともに金解禁に反対した経済評論家の高橋亀吉も認めている。
小汀自身も「持ち前の毒舌がうけたらしい。ぼくが前座をつとめると聴衆が先へ帰ってしまうので、たしか3回目あたりからぼくが真打ちをやらされた思い出がある」(『私の履歴書』)と自他ともに認める弁士だった。
講演は人気があった。50年に公職追放が解除され、日経顧問として講演や執筆活動をするようになるが、毎月、大阪を訪れて講演した。大阪編集局の配属になった小島章伸(51年=昭和26年=入社・外報部長、編集局長などを歴任)はたびたび大阪駅で小汀を出迎えた。「社長までやった人が3等車に乗ってくるのには、びっくりした。固定ファンがいた。話は面白かった。講演を聴いて、大阪版用の原稿を何度か書いた」と思い出を語る。
対談の記録も残っている。68年に「天に代わりて」と題した三島由紀夫とのやりとりは次のようにはじまる(三島由紀夫対談集『尚武のこころ』日本教文社・70年刊)。
三島「きょうのテーマは〝天に代わりて〟だそうですが、小汀さんが〝天に代わりて〟の役で、私は不義の方ですかな。(笑い)討たれの方ですね。両役がないとチャンバラになりません」
小汀「いや、ぼくは年中つまらんことを発表していて社会に害悪を流しているから、あなたが主役で私が拝聴役だ」
もちろんしゃべっているばかりではなく、書いたものでも面白いのがある。
石橋湛山が正統派の言論人として知識層に訴えかけていたとすれば、小汀は路地裏派のエコノミストとして市井の人々にもわかりやすく経済を説いていた。
『街頭経済学』(千倉書房・31年刊)がその例だ。好評につき翌32年には続編の『漫談経済学』を同じ出版社から刊行した。
『街頭経済学』のはしがきに「われわれ日常街頭に於いて見るところの諸現象をば、専ら経済的見地から観た」とあるように、身近なできごとに経済という物さしをあててみせている。
同時に「此の書は書斎に立て籠もって、鹿爪らしく読まるべき物では無い、寝転んで読み、通学通勤中の電車の中で読み、また旅の伴侶として携えて行かれることが著書の希望である」と内容も読みやすいものとなるよう心がけている。
経済部長のころの著書だが、問答形式なども多用して、街角の経済だけでなく金輸出の再禁止についてかみ砕いて論じたりと縦横無尽だ。
たとえば『漫談経済学』の「婦人経済学」の章では、家庭の貯金の心得として①余裕ができたら貯めよう②不規則に断続的に貯めよう③合理的にでなければ貯めないーーでは貯金は絶対にできないとして、物を売ったり借金してでも貯金していく「不合理的」貯金法を勧める。夫婦相和しての「夫婦愛貯金」の提案などユーモラスなものもある。
「野球経済学」の章もあり、野球の試合を観戦する客で交通機関は大きな収入になり「電車会社が野球に目をつけるのは当然である」として、大学野球全盛の当時にあって「職業野球団をつくる」よう促している。こうした指摘をみても先見の明があったことがわかる。
現実の動きを経済的な視点でとらえ、肩ひじをいからせずに、その意味するものやこれからの流れを示していくところに小汀の真骨頂があった。
ただ記者のあり方には厳しかった。34年、編集局長になったとき人事の大刷新を断行した。『私の履歴書』で次のように書いている。
「何しろ新聞記者といえば、人と会うとき、鳥打ち帽子をかぶり、レーンコートを着たまま、机の上へ足をのせるような無礼きわまるやつさえいた時代で、そういう能なし記者を片っぱしから片付けた」
「ある記者のごときは芸者を女房にして待合を経営させていたので、自分は左うちわで新聞記者をしていたが、記事はいっこうに書かない。そのほか、会社、銀行を食い物にしている不良記者、出勤常ならざるぐうたら記者など十人あまり、つぎつぎに引導を渡した」
牧歌的な記者が大勢いたのである。そんな時代だった。
新聞記者を志す若者へも甘い言葉は発しなかった。
自由学園最高学部の永田晨(53年=昭和28年=入社・外報部長、アメリカ総局長などを歴任)は入社試験を受けるにあたり自由学園の創立者である羽仁吉一の紹介状を持って、日経顧問の小汀に会いに行った。
「記者、記者と言うが、煙をシュッポ、シュッポと立てて、〝汽車〟のように自分で走れる記者になれるものは、千人に一人。あとは皆押さないと動かぬトロッコばかりだ」
小汀がとりつく島もなかったことを永田は覚えている。
この話には後日談がある。72年、小汀が永眠した直後、小汀夫人から永田のもとに手紙が届いた。そこには20年前の羽仁から小汀にあてた紹介状が同封されていた。「少々整理をしていたところ、同封羽仁吉一先生のご消息が出てまいりました。......文面が貴方様のご関係のことゆえ......お手元に差し上げます」と美しい巻紙での手紙だった。
夫人ともども礼を重んじ、義理を欠かさぬ人間性がそこにはあった。
だから小汀は、新聞記者は礼儀正しくなければならないと厳格だった。その背景には、中外商業の記者になる前に島田衆院議長の秘書をしていたときの原体験もあった。
50年たっても嫌な記憶は消えなかった。社会人としての常識ある行動を新聞記者に求めたのはそのためだった。
5. 大勢順応主義者?
当然のことだが、小汀を手放しで持ち上げようとは思わない。3つの顔を持つといっても、その顔はだれが見てもすべて端正ということはまずあり得ない。完璧な人間など、この世には存在しない。良いところも悪いところもすべてを含めて評価すべきだ。そのとき有益なのが他者の目である。そこにはまた違った風景が浮かんでくる。
小汀を厳しくみていた人間に、徹底した自由主義者だった評論家の清沢洌がいる。米国から帰国後、20年に中外商業に入社し、23年に初代の通報(外報)部長となった。27年まで在職したので短い期間だが小汀と一緒に編集局で仕事をしていた。
清沢著『暗黒日記』(岩波文庫)から小汀に関するくだりをひろってみよう。
岩波文庫版での山本義彦(元静岡大教授)の注釈は、小汀について「清沢は交流が深かったが、しかし彼の大勢順応主義的傾向にたいしては厳しい見方をしていた」とある。清沢は小汀にけっこう冷ややかだった。大勢順応主義とは、しばしばリアリストに向けられる批判のつぶてである。たしかに、そこには現実主義の罠(わな)がひそんでいる。注意をしなければならない点だ。
人間の存在というのは相対的なものである。清沢からみて、たしかに石橋湛山らに比べると小汀はそうだったのだろう。桐生悠々(信濃毎日新聞)や菊竹六鼓(福岡日日新聞)が展開した反軍的な言説に比べても、中外商業が微温的で不徹底だった、と現時点で批判するのはやさしい。しかし先に述べたように小汀が決して唯々諾々と戦争の旗振り役を演じたのでないことだけは確認しておいていい。
『暗黒日記』にはこんなくだりもある。
44年4月15日「小汀利得は常にいう。役人という奴は、どうしたら国をつぶすことができるかと、そればかり苦労していると。奇警な言だが真理あり」
一貫して軍部や官僚を批判していた小汀。それは一本筋が通っていた。
だが61年に勲一等瑞宝章を受章している。当時のある編集幹部は「ご本人はくれるというからもらったんだという話だったが、円城寺次郎社長が『ヘナチョコ』などと官僚批判をしていたのにいかがなものかと首をかしげていたのを覚えている」と明かしていることも付け加えておく。
日本経済新聞とはどんな新聞社かと考えるとき、すっかり過去の人になってしまっている小汀だが、ふり返ってみる価値のある人物だ。
自由主義者、現実主義者そして啓蒙主義者。特に持ち味の毒舌には物事の本質をとらえた鋭さがあったから多くの共感が得られたのだろう。小汀のジャーナリストとしての生きざまは、われわれに多くのことを教えてくれているのではなかろうか。
《参考文献》
- 「私の履歴書」(1971年2月・日経朝刊掲載)=『小汀利得 ぼくは憎まれっ子』(日本図書センター版・2001年)、『私の履歴書ー反骨の言論人』(日経ビジネス人文庫版・07年)
- 『街頭経済学』(千倉書房・31年)
- 『内外経済の諸問題』(平凡社・31年)
- 『漫談経済学』(千倉書房・32年)
- 『天に代りて』(中央公論社・59年)
- 『ヨーロッパ弥次喜多旅行』(実業之世界社・65年)
- 『毒舌闘争50年』(日新報道・70年)
- 三島由紀夫対談集『尚武のこころ』(日本教文社・70年)
- 東京12チャンネル報道部編『証言・私の昭和史』(文春文庫版・89年)
- 三好徹著『評伝 緒方竹虎』(岩波現代文庫版・06年)
- 山田風太郎著『戦中派虫けら日記』(ちくま文庫版・98年)
- 清沢洌著『暗黒日記』(岩波文庫版・90年)
- 社内報・太陽樹94年8月号「先輩が語る日経―戦後50年特別企画」
- 中外商業新報 29年7月、11月~12月の金解禁関連記事(37年12月28日付)
冒頭の表現は高浜虚子の句「去年今年(こぞことし)貫く棒の如きもの」からの引用