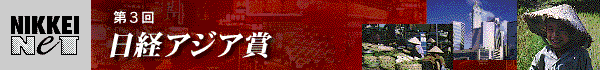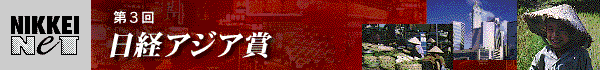「今回の受賞の栄誉は、私たちだけが浴するものではありません。マレーシアの天然ゴムにかかわる農家、産業界の人にとっても大きな名誉なのです」
「今回の受賞の栄誉は、私たちだけが浴するものではありません。マレーシアの天然ゴムにかかわる農家、産業界の人にとっても大きな名誉なのです」
「消費者の寄与も忘れてはなりません。彼らの厳しい声が、マレーシアのゴムの品質を大きく向上させる原動力になったのですから。受賞者の中には消費者も含まれていると思っています」
クアラルンプール市内のマレーシアゴム研究所(RRIM)で、マレーシアゴム局(MRB)のアブドル・アジズ専務理事は息もつかずに一気に話す。
長い伝統をもつRRIMは、ことし初めに天然ゴム関連の他の2つの組織と統合、MRBとして新発足した。母体になったのはRRIMで、MRBになっても業務の90%以上は研究開発だ。アジズ氏はRRIMの所長でもあり、文字通りマレーシアの天然ゴムの研究、生産、利用の各面での指導者の1人である。
今回の日経アジア賞技術開発部門の受賞者が個人ではなく団体になったのは、RRIMの長年にわたる世界を舞台にした活動実績を評価してのことで、その成果は多くの人の努力の集積によって生まれたからだ。
およそ150年前にブラジルから持ち込まれたゴムの木は、よほど風土が合ったのだろう、マレーシアの地にしっかり根付き、同国を代表する木になってゴム産業を育てた。
RRIMは長年、ゴムの木の品種改良、疾病の防除などに力を入れてきた。その成果で、40万戸の、小規模農家が多いといわれる天然ゴム生産者の経営改善が大いに進んだのはよく知られている。
また、天然ゴムの利用法の開発にも取り組み、いち早くマレーシアゴム標準を確立して、天然ゴムが工業素材として優れたものであることを世界に知らしめた。
この努力は現在も続いており、天然ゴムを新しいエンジニアリング素材として利用する道を模索している。「ゴムに関するあらゆる研究開発を通じて、マレーシアの産業の核を作っていくのが私たちの目標であり、使命なのです」とアジズ氏は言う。
その中核になる施設を訪ねた。
クアラルンプール市の中心部から車で30分ほどのスンガイブローにRRIMの実験ステーションがある。1300ヘクタール余りの敷地の中に栽培試験農園や育種場、ゴム製品の開発センター、試験センター、研究所をはじめ作業者の住宅や子弟の通う学校まで備えたゴムの一大センターだ。「単一商品に関する世界最大の研究機関」とRRIMが自負するのもうなずける。
研究所の中で、1つの新しい試みを見た。遺伝子工学の手法を用いて、ゴムの木に医薬品を作らせようというのだ。
「ゴムの木は樹液をたくさん出します。その中に、有用な物質を分泌させるのが狙いです。すでに技術の基盤はできました」と、バイオテクノロジー及び戦略研究部門長のH・Y・イェン博士は語る。
牛や羊の乳汁の中に薬品やワクチンを分泌させる試みは各国で研究中だが、植物ではきわめて珍しい。ゴムに関する基礎研究や豊富な知識をもつRRIMならではの仕事だ。
現在、世界の天然ゴムのシェアは約40%。しかし、耐久性や対油性が高いという特徴が見直されて、天然ゴムの消費は増加傾向にある。
マレーシア政府は、1996年から10年の予定で進んでいる第二次産業開発計画の中でゴム産業のさらなる育成を大きな柱にしている。マレーシアゴム研究所は、通称ラバーシティー(ゴムの町)という天然ゴムに関するセンター作りを通して、この計画の中核組織になろうとしている。(編集委員 中村雅美)
<略歴>
ゴム栽培業者が1900年に共同で設立した研究機関が母体に。25年に国の機関としてマレーシアゴム研究所の名称で植物学、化学、土壌学、病理学の4部門に20人のスタッフをもつ研究機関として発足した。27年に実験農場を創設、37年に現在地に本部を構えた。ゴムの木の品種改良から栽培技術、天然ゴムの産業利用、普及まで活動の幅は広い。98年1月からはマレーシアゴム局傘下の研究機関として活動している。
記念講演はこちら
|